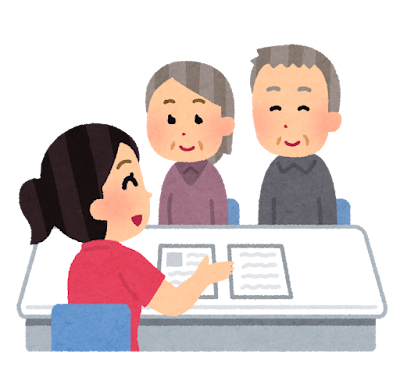COLUMN
資産承継 「相続財産の配分(遺留分)」について
- 信託
遺留分とは、生前贈与や遺言、信託等で資産の承継を行う被相続人の相続財産につき、一定の範囲の相続人が請求できる最低限取得することのできる割合のことです。例えば、配偶者と子どもがいるにも関わらず、「知人に全ての財産を渡す」という内容の遺言書を故人が作成していた場合には、配偶者と子どもは、その知人に対して遺留分を請求することができます。
それでは、この遺留分は誰がどのくらいの割合を請求できるのでしょうか。
まず、遺留分を請求できる人、「遺留分権利者」は、被相続人の配偶者、相続人である直系卑属(子、孫など)と直系尊属(父母、祖父母など)になります(民法1042条)。すなわち、被相続人の兄弟姉妹は相続人となることはありますが、遺留分を請求することはできません。
次に、請求できる割合につきましては、民法上で定められており、配偶者、直系卑属(子、孫など)が相続人である場合は各相続分の2分の1、直系尊属のみの場合は相続分の3分の1となります(民法1042条1項)。例えば、相続人が配偶者と子ども2名の場合は、配偶者の相続分が2分の1であるので遺留分が4分の1、子どもはそれぞれ相続分が4分の1となるため遺留分は8分の1ずつとなります。
なお、相続人が配偶者と兄弟となる場合には、兄弟は遺留分を有しないため、配偶者が2分の1の遺留分を有することとなります。
生前贈与や遺言、信託により、財産の承継先を決める場面において、遺留分を全く配慮せず、遺留分を侵害する場合には、その受遺者等(財産をもらう方)が遺留分の請求を受け、その対応で心身の負担となったり、相続トラブルに発展してしまったりするケースがあります。そのような事態を防ぐためにも、遺留分を配慮することはとても重要になります。
しかし、そうは言っても、特定の人に財産をまとめて遺したいというご事情がある場合もよくあります。そのような遺留分を侵害する内容で遺言書等を作成する場合には、①財産を多く渡す人には、遺留分侵害額請求に対応できるよう金銭を多く取得させる、②財産を渡す人を保険金の受取人に指定し、遺留分侵害額請求があった場合に備える、③遺言であれば、付言事項(遺言書の条文とは別で法的効力はない記載事項)に財産の配分がそうなった経緯、事情の記載を残し、遺留分を請求しないよう、理解を求めるなどの対応も重要となってきます。
私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。
(お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)
あわせて読みたい!
 | 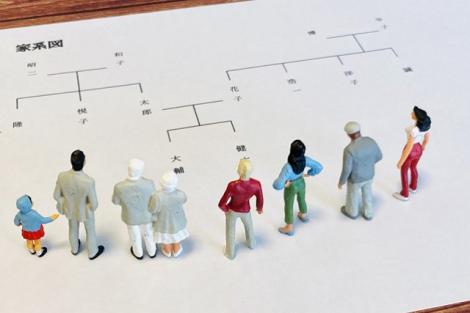 |
| 民事信託(家族信託)と商事信託の違い | 信託活用事例【海外編】 |
サービスのご案内
 |  |  |
| 日税民事信託コンサルティングサービス | 日税事業承継支援サービス | メールマガジンのご登録 |
免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。
株式会社日税経営情報センター